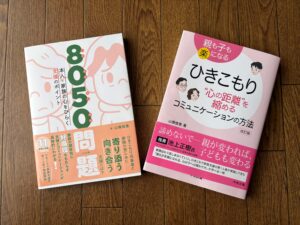令和7年第3回定例会 9月議会報告
9月2日から26日まで、第3回定例会9月議会が開催されました。
本議会では、令和6年度の各決算審査が行われました。
令和6年度一般会計決算認定については、議長と監査委員を除く16人の議員で構成される令和6年度一般会計決算審査特別委員会を設置して審査が行われました。
決算額386億92,525,987円が全会一致で認定されました。
令和7年度一般会計補正予算第5号では、防災食育センターに係る修繕費や市営競技場等の夜間照明の改良工事、せせらぎ遊歩道公園法面対策応急工事や多摩川堤防沿桜伐採工事など15億96,752,000円が可決されました。

一般質問
1、化学物質過敏症や香害に関する啓発等について
福生ネットが主催した啓発のための「香害パネル展」には、市内外から多くの方にご来場いただき、大きな反響があったことを踏まえ、市の相談体制や啓発等の現状について質問しました。
(香害パネル展を開催しました | 福生・生活者ネットワーク)
香害や化学物質過敏症の方を把握していないが、保健センターや健康相談、消費者相談において随時相談できる体制である。5省庁作成の啓発ポスターは、消費者相談のあるもくせい会館に掲示。学校では、文部科学省からの依頼文及びポスター「香りの配慮に関する啓発資料」を校内で掲示し、児童や教職員、保護者等への周知を行っている学校もあるとの回答でした。
先ずは、ポスター掲示を増やすことと市民・保護者への周知・啓発を要望しました。
2、市有施設における温室効果ガスの排出量の削減について
2025年2月26日に市が行った「福生市ゼロカーボンシティ宣言」の具体的な取組の一つとして、市有施設における温室効果ガスの排出量削減の取組について質問しました。
本庁舎でのESCO事業(空調設備の更新及び照明機器のLED化等を実施し、老朽化した設備の刷新と省エネルギー化を図った)の省エネルギー化効果は、3か月間の更新前と更新後の消費電力量の比較で約44%の削減効果、二酸化炭素排出量は約47%の削減効果があった。市有施設のLED化率は26.5%で、令和12年度完了予定であるとの回答でした。
今後、公共施設総合管理計画の中で、ZEB化(Net Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の略称。建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物のこと)に対する市の考え方や目標を明確にすること、PPAモデル(PPA事業者が、市の保有する建物の屋根等に太陽光発電設備を設置し、そこで発電した電気を買い取って使用する仕組み)や「エコスクール・プラス」(学校施設を環境・エネルギー教育の教材として活用する仕組み)等の多様な手法について調査研究するようを要望しました。
3、防災行政について
(1)自助に関する取組について
避難所が快適な場所となることが難しいことから、自宅の倒壊や浸水等の危険がない場合は在宅避難することがすすめられています。
在宅避難を基本とする考え方から、市民一人ひとりが災害を想定した準備をすることが重要になってくると考えます。
市民が備蓄等の備えを行うための周知・啓発の取組について、また、一人ひとり事情の異なった障がい者や高齢者のいる家庭への取組について質問しました。
ハザードマップ等で周知に努めているが、具体的な内容について福祉関連部局と協議していくとの回答でした。
各課が防災について考えるための会議体の設置、また、防災担当と各課が連携して自助について考え情報発信するよう要望しました。
(2)災害時の健康に関する取組について
災害時に避難所や在宅避難などの避難生活を送る場合、生活環境の急激な変化や、十分な医療・栄養が得られないことが原因で、健康状態が悪化することがあります。
災害時に市民が健康状態をできるだけ良好に維持できるよう、災害時の食に関する取組について質問ました。
非常時における健康のための栄養バランスやレシピについて、他の自治体の取り組みを参考に庁内で議論していくとの回答でした。
4、ひきこもりへの理解促進と支援の拡充について
ひきこもりに対する理解を広げることや支援者を増やすことが重要であると考え、市の考え方や取組について質問しました。
ひきこもりの状態にある方やそのご家族に対する取組については、生活にお困りの方への相談の中で当事者の方やその御家族に関する情報が得られた場合、必要に応じてアウトリーチによる訪問支援を行っている。また、重層的支援体制整備事業として、社会福祉課の窓口が福祉の総合相談窓口となり、ひきこもり当事者の方からの相談に対応するだけでなく、御家族や近隣の方々からの支援要請も含めて、包括的相談支援を行っている。
また、地域の支援者である民生委員が研修を受講し、支援に関する基礎的な知識のほか理解を深めていただく機会を設けているとの回答でした。
一番身近な支援者である家族が、理解を深めることや課題解決に向けた具体的な当事者への接し方等の知識を得るための取組を要望しました。

令和6年度一般会計決算審査特別委員会
以下のような質疑を行い賛否の判断としました。
また、本会議最終日に賛成討論を行い、全会一致で認定されました。
●行政改革の取組について
●ウクライナ避難民生活支援給付事務について
●公共施設マネジメントの地域懇談会の取組について
●ふるさと納税による住民税の流出額について
●定額減税調整給付金給付事業について
●中間処理事業の容器包装プラスチック処理委託料等について
●地域自立支援協議会事務の専門部会について
●介護サービス事業所支援事業の補助金の活用について
●男女共同参画事業の子ども向けガイドブックについて
●幼保小中連携事業の講演について
●特別支援教育事業の指導補助員について
●給食調理事業の生ごみ処理機の稼働と発電プラントへの搬入について
など

討論
本会議最終日に、3件の討論を行いました。
●令和6年度福生市一般会計決算認定
令和6年度は、令和5年度に引き続き、エネルギーや食料品価格の高騰など物価高騰に対応した年であったと決算審査からも感じております。特に、国のデフレ対策である定額減税調整給付金給付事業は、制度が複雑であり、事務量が大きく増加しましたが、適切な給付となるようご努力いただいたことも確認いたしました。
大変厳しい社会情勢が続く中ですが、福生ほたる祭りが5年ぶりに開催されるなど、さくら祭り、七夕まつりに続き、福生のまちに元気がまた一つ戻ってきた年でもありました。
令和6年度の組織改正では、こども家庭センター課の新設や障害福祉課の再編、教育支援課の再編など、社会課題に柔軟に対応できるよう見直しが行われました。
審査においては、行政改革の取組として、評価サイクルを3年から2年で一巡できるよう見直し、よりスピード感を持って事業改善に活用できる体制を整備したことを確認しました。また、即時文字起こしシステムの導入で、相談業務等の効率化を図ったことは、職員の負担軽減とともに、相談内容が伝わりやすく、市民の相談に寄り添うためのしくみとしても有効であると考えます。組織改正と行政改革の取組について評価いたします。
国のこども家庭庁設置やこども基本法の成立を受け、福生市においても令和5年度に子ども政策課を設置し、「子育てするならふっさ」とともに「こどもまんなかふっさ」を掲げ、子ども施策を推進されてきましたが、令和6年度はその2年目となり、こども計画の策定に取り組み、「こどもまんなかふっさ」が定着してきた年であると感じております。
子どもと子育て世帯への支援体制を強化のための「こども家庭センター」の設置、里帰り出産に対応した産後ケアのさらなる充実、「児童発達支援センター」の設置、「多文化キッズサロン」開設準備のための設置工事など、多様な子どもたちと子育て世帯に寄り添うための事業を評価いたします。
教育行政につきましても、公民館での子ども企画講座やジュニア司書養成講座の実施などの新たな取組とともに、スタディ・アシスト事業は事業として定着し参加者も増加しています。「令和の記憶・記録プロジェクト 未来に残したい福生の風景写真コンテスト」は2か年にわたる事業ですが、児童生徒のかかわりもあり、これらの多くの「こどもまんなかふっさ」に資する事業を評価いたします。
また、教育委員へのタブレット端末の貸与等、事務の効率化を図る取り組みを確認し、また、公民館職員の資質向上のための取組を審査において確認しました。今後の取組に活かされることを期待いたします。
以上のことから判断し、令和6年度福生市一般会計決算の認定に当たり、賛成であることを申し上げまして討論といたします。
●日本政府に核兵器禁止条約の署名、批准を求める意見書の提出を求める陳情書
ノルウェー人民援助(NPA)がアメリカ科学者連盟(FAS)と協力して発表した「核兵器禁止監視報告書」によりますと、2017年に国連が核兵器禁止条約を採択して以降、老朽化した核弾頭の廃棄によって核弾頭の総数は徐々に減少してきたが、実際に使用可能な核兵器の数は2017年の9272発から2024年初めの9585発、2025年初めには9604発へと着実に増加しているとのことです。この数は、広島に投下された原爆の約14万6500発分に相当するそうです。そして、これらの核兵器の約40%は、潜水艦や地上配備ミサイル、爆撃機基地に配備されており、即時使用が可能な状態にあるとされています。
日本は核兵器不拡散条約NPTに署名・批准しています。被爆国として、核軍縮・不拡散・原子力の平和利用の三本柱を重視し、NPT体制の強化に、また、核兵器国と非核兵器国の橋渡し役として積極的に貢献していると認識しておりますが、現に核兵器は増え続けています。
2010年NPT再検討会議では、核兵器国5か国を含む189か国のすべての締約国が「条約の目的にしたがい、すべてにとって安全な世界を追求し、核兵器のない世界の平和と安全を達成することを決意する。」こと「保有核兵器の完全廃棄を達成するという核兵器国の明確な約束を再確認する。」こと等で一致し、それら「枠組」を創るために「特別の努力」をすることに合意しましたが、その後、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻など悪化する国際情勢を受け、2015年、2022年と、すでに2回続けて最終合意文書を採択できないでいます。次回は2026年の予定です。それに先駆けて、今年2025年4月には第3回準備会合が開催されましたが、来年の再検討会議において議論の指針となる勧告文書を採択できないまま閉幕しました。
現在、核兵器を保有するのは9か国で、核兵器国5か国以外にも未加盟国のインド、パキスタン、イスラエル、北朝鮮が核兵器を保有し、そのほかに保有が疑われている国もあり、核兵器不拡散条約だけでは対応しきれない現状があります。
このようなNPT体制での核廃絶が進まない現実に対して「核兵器がなぜいけないか」という原点に立ち返ったのが広島・長崎の被爆者の中から興った、核兵器を作るのも使うのもの人道に反するという声に基づいた、包括的な核兵器禁止で合意しようという、核兵器禁止条約です。核兵器禁止条約と2010年NPT再検討会議の合意とは、目指す方向性は一致しているものと考えられ、日本政府が核兵器禁止条約に署名批准することに矛盾はないと考えます。また、威嚇・開発・生産・実験・製造・取得・保有・貯蔵など核兵器にかかわる全てを禁止し、被爆者や核実験被害者への援助を行う責任についても明記され、これに日本政府が署名・批准することは、究極的な核兵器廃絶に向けた核軍縮の機運を醸成することそのものであると考えます。
以上のような理由から、本陳情を採択することに賛成であることを申し上げて討論といたします。
●福生市中央体育館に関する陳情書
この陳情書は、福生市中央体育館の点検と点検後にそれに応じた修繕等の対応を求めるものです。
陳情の要旨に記載のある修繕の必要な個所については、すでに対応されていることが委員会の質疑で明らかになっており、また、担当職員が体育館の会館前に目視による点検作業を行っていることが質疑によって確認されております。
本陳情書には、「スポーツを安全に楽しみ、交流などを深める大切な場だと思います。」また「これからの市民と安全と健康、日々の楽しみのために、どうか体育館の点検、修繕をお願いします。」と記されておりまして、陳情者にとっての大切な場所であることがわかります。それと同時に安全にということが強調されているように受けとることができます。
他市の事例ですが、今年5 月8日には、S&Dスポーツアリーナ羽村の第1ホールで、天井材に使用している気泡コンクリートの破片が落下する事象がありました。専門業者による検査点検が行われ、安全が確保できるまでの間、一部が貸出し停止となっています。羽村市が施設の現状把握をどのように行っていたかはわかりませんが、想定外のことであったと思われます。
陳情書には、どのような点検をしてほしいという具体的な要望はありませんが、他市の事例を考えますと、福生市中央体育館の専門業者による検査点検の必要性を感じるところです。また、安心して利用していただくため、安全性や修繕が必要であるか否かの判断や情報等を、利用者へ説明することも必要であると考えます。
利用者の安全確保のための、担当職員の日々のご努力には感謝するところではございますが、それだけで十分であるとは言い切れないところがあると考えます。
以上のような理由から本陳情を採択することに賛成であることを申し上げ討論といたします。